↓メッセージが聞けます。(日曜礼拝録音)
【iPhoneで聞けない方はiOSのアップデートをして下さい】
➀この日、主イエスは、ナインという町に行かれました。
このとき、イエスさまのその後を大勢の人々がついて来ていました。
・そしてその町の、門のところまで近づいた時、その町から一つの柩(ひつぎ)が担ぎ出されるところでした・・。
・その柩は・・母一人子一人で生きて来た、その一人息子の柩でありました。
・12節のところをよく見るとこのように記されています。
朗読→「町の人たちが大ぜいその母親に付き添っていた・・。」
・そうです。この母親の、その悲しみの深さがこの町人たちにはよくわかっていたのです。
ですから、大勢の人たちが、深い悲しみの中にある、この母親に付き添っていたのでした・・。
・当時、夫を失った女性が生きてゆくことは非常に困難なことでした。ですから・・この二人は・・毎日食べるだけでやっとの、言わば最底辺の生活をしていたのではないかと想像できます。
・しかしこの母親がここまで生きて来られたのは・・この一人息子がいたからこそであったのでありましょう・・
・この母親は・・「この息子のために、がんばらなくては・・」その一心で、きょうまで、なんとか生き抜いて来たのではないか・・そう想像できます・・。
・つまり、この一人息子は・・彼女の、正に支えであった。・・正に生甲斐であった・・いや、自分のいのちよりも大切な・・そういう存在であったに違いありません。
・「その我が子が今死んでしまった。」その深い悲しみの中にこの母親はいたのでした。
・あるいは・・もしかすると・・この息子は、青年と言っても、もうすっかり成人していて・・この母親と暮らしていたのかもしれません。 この母親を守って・・都会に出てゆく夢を捨てて、この小さな街でなんとか仕事を見つけ、そしてこの母親を養っていたのかもしれません・・。
・いずれにせよ、この母親の悲しみは、私たちの想像を超えた深い深い悲しみであった・・私たちはそのことを覚えながらここを読んでゆきますと、この個所の神さまからのメッセージが見えて来る‥私はそう思うのです。
➁この先の13節を見ますとこのように書かれてあります。
→ 主はその母親を見て、かわいそうに思い、「泣かなくてよい」と言われた。
・この「かわいそうに思う」という言葉を見て、みなさんはどういう風に思われるのでしょうか・・。何でもない言葉の様に感じるのではないでしょうか・・
・しかし、聖書学者たちは、この言葉は、実は注目すべき言葉であると言うのです。この「かわいそうに思う」という言葉は、共観福音書といわれる、マタイ、マルコ、ルカ、この三つの福音書だけに使われている、特別な言葉でとても大事な言葉であると言うのです。
○ではこの言葉は、他では・・どのような場面で使われているのでしょうか・・
・先ず有名なのは、皆さんも良く知っておられる、あの「放蕩息子のたとえ話」・・あの話の中で・・あの弟が・・父の所に帰ろう・・と、決心して、家に戻ってゆく場面その場面で使われています。
・この息子は、自由になりたい、自分の思った通りに生きてゆきたい・・そう思って、家を飛び出し・・好き勝手に生きてみたのです。
・すると・・確かに、始めは、楽しかった・・面白かった・・しかし、自分の思いのままに生きる・・という歩みは・・次第に、行きづまってゆきました。 そして、ついには、どんずまりになってしまうのでした。
・父親からもらった遺産は、瞬く間(またたくま)になくなり・・彼の生活は、次第に、乱れて・・気が付くと、彼は、ブタが餌を食べている、その前に立っていました・・。
・そして、その豚が食べていた、イナゴマメを・・「自分も食べたい・・」そう思うほどになっていたのです。 つまり、豚以下の生き物となってしまったのでした。
・その時です。彼は・・我に返って、こう思ったのです・・「そうだ、父の所に帰ろう・・」
勿論、あつかましく息子として帰るわけにはいかない・・でも、帰れば・・きっと父は、使用人のひとりくらいにはしてくれるかもしれない・・」 こう思った彼は・・父の家に、恐る恐る帰ってゆくことにしたのです。
・彼が帰ってゆく・・その道で・・ そこは、まだ、父の家までは遠かったのですが・・誰かが、向こうから走ってきました。 よく目を開けてみると・・何と、それは父親であったでした。
・父親は、その息子を見つけ、・・かわいそうに思い・・口づけし、彼を抱きしめます・・。
・この時に、使われている言葉「かわいそうに思い」という言葉、これがきょうの聖書個所にある言葉と同じなのです。
○もう一つ例を上げますと・・これまた、皆さんがよくご存知の、よきサマリヤ人の譬え話あの有名な主イエス語られたたとえ話です。
・旅先で一人の旅人が強盗に遭い、半殺しの目に遭い・・道に倒れていた・・ いろいろな人がそこに通りかかったのですが、皆、何もしないで・・通り過ぎてゆくのでした・・
・ところが・・ユダヤ人と対立関係にあるはずの、サマリヤ人が通りかかる・・すると、このサマリヤ人は・・「彼を見てかわいそうに思い」・・この重傷を負い、死にそうになっていたこの旅人を介抱するのでした。
・この時にも、きょうの箇所と同じ言葉が使われています。・・「彼を見てかわいそうに思い」と訳された言葉です。
③この二つの聖書箇所は、どちらも譬え話です。 そして、そこに出てくる父親、また・・サマリヤ人・・これは、イエスさまご自身の姿を現しているわけです。
・そして・・その愛の方が、苦しみあえいでいる人を見つめる・・そして行動を起こされる・・その痛んでいる人を抱き全力で介抱してゆく・・このときのこの「かわいそうに思い」という言葉は・・その行動の、動機となっていった、イエス:キリストの心の内を現した言葉なのです・・。
○先日、・ある新聖書注解書を読んでおりましたら・・この「かわいそうに思い」という言葉の解説が出ておりまして・・(その解説は、榊原康夫先生が書いているのですけれども・・)
この言葉の意味についてこのように説明されていました。→これは直訳すると、<腹わたを揺り動かされること>となります。
・「何か変だなあ・・」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが・・これは、実は、この言葉の元になっている言葉が「内臓」つまり「はらわた」という言葉であるからなのです・・。
○ですから・・この時イエスさまがこの我が子の柩とともに、町の門の所まで歩いて来たこの母親を見た時に思われたこと・・・
・それは丁度、放蕩息子が帰って来たときに、走り寄って彼を抱きしめた、あの父親の熱い思い・・また、半殺しのめに遭って呻いていた人を介抱し助けて行った、あのサマリヤ人のあの誠実な思いと同じ思いである訳です。
・この時、おそらくは、この母親は泣き叫んでいたのだと思います。そして、町の人たちもこの母親を支えながら、声を出して泣いていたのだと思われます・・・。
・その泣き叫ぶ声・・そして、歩くこともままならないその母親の姿を見られたときに、イエスさまは、正にはらわたが揺り動かされる思いになられたというわけです。
・この「はらわたがゆりうごかされる」ということは・・この母親への同情だけで起こることではないと私は思います・・。
・ではイエスさまの中でどんな思いがあったのでしょうか・・
私はこの、人々をこれほどまでに打ちのめしてゆく・・その死というものに対しての怒りが、イエスさまの中に今充満したのではないか・・そう思うのです。
・そしてイエスさまの中に、正にはらわたがゆれうごくような熱い思いが湧き上がり・・その思いが頂点に達し・・そしてイエスさまの口から次の言葉が語られたのだと思うのです・・。
・13節→ 主はその母親を見て、かわいそうに思い、「泣かなくてよい」と言われた。
④牧師という立場に長らくおりますと、愛する教会の方のその葬儀の司式をするという、重い役目を担う時があります。
・そのようなとき、ご家族も、そして教会も、死の威力の大きさに、もう少しで打ちのめされそうになるときがあります。
・ですから、そのような時、私は神さまからのお力をいただくために、神さまの御言葉をしっかりいただくようにしています。大抵は前日、私はきょうのこの聖書個所をよく開きます。
・そして、ここで、我が主であるイエス・キリストがこのように語られたことを確認してから床に就くようにしています。
・「泣かなくてよい!」という御言葉を心にしっかりとインプットさせます。するとこの御言葉が私の心の中でこのように響いてゆきます。「贖われている者がたとえ死の時を向かえても、それは、決定的に悲しいことではありません。この方は、まことのいのちを賜っておられるからです。ですから、もう泣かなくてよいのです。」
・そして葬儀当日もまたこのイエスさまのこのみ言葉をいただいているからこそ、そのご家族にも、教会の方々にも「この方は死に勝利しておられます。もう泣かなくていいのです。」そのように、堂々と宣言できるわけです。
⑤今日の聖書個所に戻しますが・・
・そういうわけで、主イエスがこの時、「泣かないでよい」と言われた意味ですが・・それは・・「泣いてはいけません」と言っておられるわけではありませんで・・
・主はこう言っておられるのです。
「もうこれ以上泣かなくてよいのです。 命をお与えになられる神さまは、その先の命もお与えになることのおできになる方なのです。その偉大な神さまの愛を信じなさい。」
・「泣かないでいいのです。 涙を拭いてわたしのもとに来なさい。そして、あなたが・・神の愛を受け入れ・・救い主を信じてゆくときに・・その人生において・・死は、どうしようもない敵ではもうなくなるのです・・。
・そうです。私たちの主イエス・キリストは、「もう泣かなくてよい」と言ってくださる方です。
今週も・・この主イエスの御言葉を心に秘めつつ。この方を讃美しつつ、与えられている一日一日を大切に生きてゆきたいと思います。
(上のバーから聞けない方は青いボタンから)
iPhone


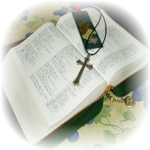


 English
English